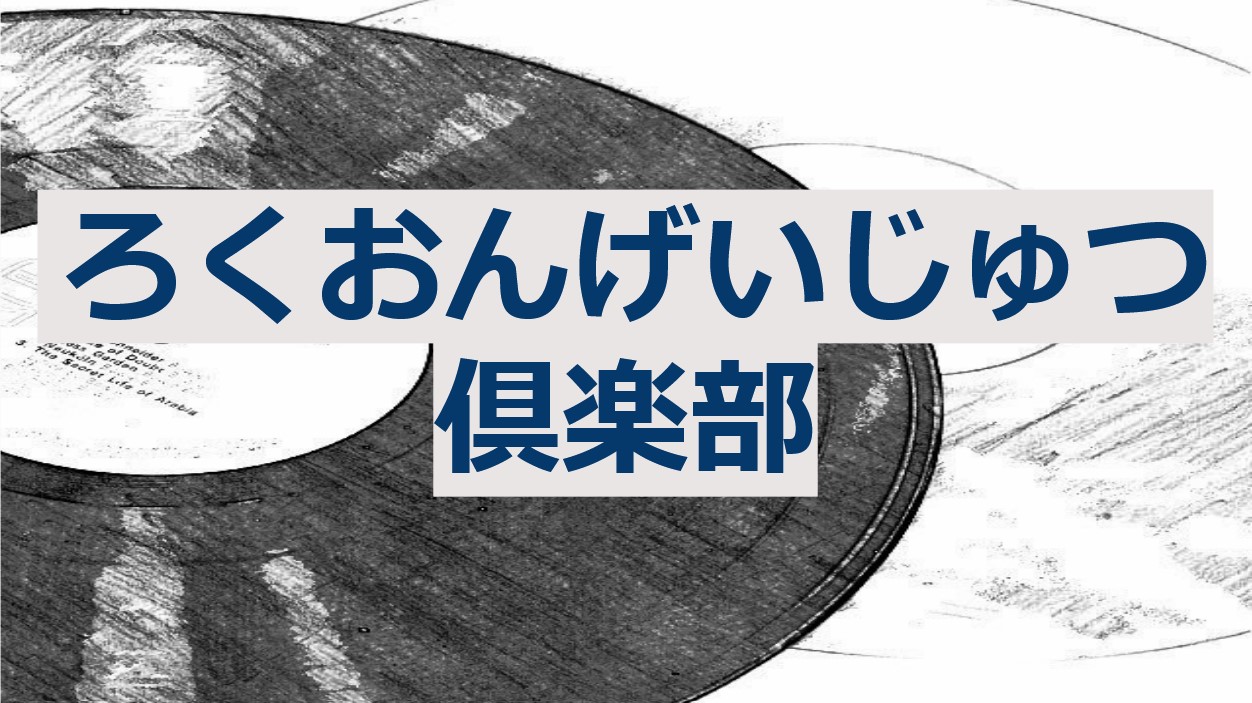W3がそんな足踏みをしている間に錦が藤田さんとやっていた絶対安全毛布は都内のライブハウスで話題になりはじめ、StraySheepsはインディーレーベルからリリースされた最初のフルアルバムがタワーレコード新宿店のインディーコーナーでポップつきで紹介されるまでになっていた。絶対安全毛布の話題は同じ大学の軽音で錦達とは全く面識がないやつから聞いた。StraySheepsのポップに関しては何の事前情報もないまま偶然見つけ、既に絶対安全毛布の口コミを聞いた後だったから錦や高岸と自分との差に改めてショックを受け、CDも買わずにふらふらと店を後にした。いつもだったら新宿西口の紀伊國屋書店で本を物色し、地下でカレーを食べ、隣のビルに入っているディスクユニオンに行き、余力があったら向かいの三越にあるジュンク堂に行くのがお決まりのコースだったが、この日は何も買わずに電車にのり、人波に揉まれながら、もういっその事就職活動を始めようかと思ったが、当時は今よりもずっと前倒しで就職活動のシーズンが始まっていたので三年生の三月の時点で何もしてないのは既に手遅れで(実際にはその時始めていてばなんとかなったとは思うのだが)、我々学生が思いつく様な主だった大企業は既にエントリーシートを締め切っているか、締切まであと何日かという状態で、そんな事を知ったのも家に帰って勇気を出してとりあえず知ってる企業の採用ページを初めて適当に見てからで、慌ててリクナビやマイナビに登録しようとするもその時点で考えたことすらない志望の職種や業界や自己アピールの記入を求められ、登録できただけでも褒めて欲しいぐらいだったが、その日馬力を出してしまったせいか、そこで力付き、バンドを続けるのか就職活動をきちんと始めるのか(両立という柔軟な考えはなかった)どっちにも転べずどうするかも分からず決められずにいつのまにか僕は四年生になった。
そんな四月に例の絶対安全毛布の口コミを聞かせてくれた友達が彼らのライブに誘ってくれた。当然錦には別れてから一度も会ってないし、絶対安全毛布のライブもそれからは見ていない。初期の彼らはまだバンドとしてギクシャクしていて、錦の良さを体現できていなかったから、その時の印象がそのままなのか、それとも更新されているのか、常日頃確認したいとは思っていた。彼は僕がその絶対安全毛布のボーカルとつきあっていたことなんて知らないし、言って遠慮されるのも嫌だったから何も言わずについていき、後ろの方で見ることにした。
会場となったライブハウスは渋谷の老舗の箱で、数多くのメジャーバンドを輩出したことでも有名で、彼らの出番はトリではなく一番目だったが、結成から一年そこそこでここで最初の出番でやれている時点ですごかった。彼らの場合は一からバンドを立ち上げたわけではなく、前身となるメソポタミア文明ズがあったこともあり、その時からのファンなどももしかしたらいたのかもしれない。会場は満員で混み合っていて錦とは顔を合わせずに済むかもしれないが、逆に人の波の中でバッタリと遭遇してしまう危険性もあってヒヤヒヤするも、トップバッターだから今頃ステージ裏で準備をしているはずでその心配は無いと思い直したり忙しなく開演を待った。そんな僕の様子をライブに誘ってくれた友人(残念ながら名前はもう覚えてない、本当に思い出せない)はよほど絶対安全毛布に期待しているのかと誤解してくれていたようで「楽しみだね」と連呼して期待で無邪気に興奮していて、彼には悪いがまたそれで苛立った。
客電が暗くなり、メンバーがゾロゾロ出てくる時点で歓声があがる。暗くてよく見えないがベースの藤田さん以外は僕の知ってる絶対安全毛布のメンバーではなかった。だが彼らはよく知っているメンバーだった。どういうことだ? 感情が一瞬でぐちゃぐちゃになった。出てきたメンバーはみなかつて錦と僕が加入しためちゃくちゃにしたバンドのメンバーばかりだった。それも皆、こいつはいいなと思ったプレイヤーばかりだった。一体どうやって? そういえば藤田さんは僕と錦が加入したバンドのライブを見に来ていた。そういうことだったのか。彼は最初から僕らが参加するバンドが上手くいかないだろうことを見越して、ライブを見に来ていたのだ。そして、そのなかでお気に入りプレイヤーがいたらいずれ引き抜こうと思っていたのだ。なぜなら彼らは錦の歌と曲に興味があるから。そうして錦を中心としたスーパーバンドを結成してしまったのだ。そもそも正直、絶対安全毛布が活動を続けるとも思っていなかった。彼女は音楽活動を全くやめてしまうとすら思っていた。それぐらい一連の解散劇で我々が負ったダメージは大きかったはずだ。そう、だからメソポタミア文明ズがSafety Blanketsに改名し錦が中心になってバンドが再スタートを切った時、錦はまだ並行してバンドを掛け持ちしていて、それが瓦解しかけていたから、Safety Blanketsもうっすら上手く行かないかもしれないと思っていた。Safety Blanketsが絶対安全毛布になった時、バンドは続いていたが、ゆるい雰囲気で錦の曲も殆どなく、藤田さんが作って他のメンバーが歌う曲と錦の曲と、みんなでジャムって作ったファンクナンバーが混在していた。おそらくその活動を通して彼女がバンドをやりやすい雰囲気づくりをしていたのだと思う。だから初期の絶対安全毛布のあの緩さ、それは意図的なものだったのか。今日みた絶対安全毛布はもっと隙のない、恐ろしく完成されたバンドだった。何か変わったのか。おそらく藤田さんは徐々に錦中心の体制に整えていったのだろう。長い目でもって。その為にメンバーも変えた。いや就職活動や卒業で自ずと変わっていったのかもしれない。久々にみる錦に何らかのダメージを受けるところまでは覚悟していた。まさか錦が出てくるまでにこんなダメージを受けるとは思ってもみなかった。最後に遅れて錦が出てくる。髪が少し伸びてセミロングになっていてメガネもしていなかった。一部の親密な人間にしか見せていなかった彼女は全世界に公開されていた。ますます帰りたくなったが彼らがどんな音を奏でるのかという好奇心には勝てず、そこから動けなかった。
僕が知っていた錦の楽曲はポップでありながらダンサブルな、ニュー・ジャック・スウィング以降のR&Bみたいな楽曲だったし、メソポタミア文明ズはファンクバンドだった。その流れで絶対安全毛布の最初期もファンクバンドだったから、アコースティックギターの柔らかなリフが最初に流れてきたのは意外だったが、そのリフに乗せて錦がマイクを持って踊りながらご機嫌に歌い始め、徐々に楽器が加わってきて盛り上がり、結局はストーンズの「無常の世界」やプライマル・スクリームの「movin’ on up」みたいなゴスペル調のポップでアッパーでダンサブルなナンバーという事が分かった。という分析は後で冷静になって振り返った時に気づいた事でその時はもう興奮の渦に巻き込まれてまわりの観客と一緒に体を揺らしていた。途中から錦はステージ端に移動してそこにあったキーボードを弾いてサザンロックやカントリーみたいなコロコロと鍵盤上を指が転げ回るような軽快なピアノソロを弾き、ソロパートが終わるとそのままそこで歌った。曲は最高潮に盛り上がったまんまで終わって、その瞬間に観客の叫び声がこだました。間髪入れずにクリーンなギターサウンドがかき鳴らされ次の曲が始まる。この曲の事は今でもビビッドに思い出せる。さっきのとは違って若干の憂いを帯びたようなメロディが特徴、だが同時に踊れる曲で、マイクを持って中央に出てきてはリズムに合わせて自然に体を揺らしながら彼女は歌った。去っていった楽しい時代について懐かしむ様な曲で、僕の中ではそれは彼女との思い出で、それらがダイジェストで駆け巡った。何しろその当人が目の前にいるのだ。彼女の凄みがこんなポップな方面に振り切られて提示されるとは思ってもみず、何度も言うけど当時のライブハウスはナンバーガールや銀杏BOYZといった激しいサウンドやポストロックやポストパンク的な実験的かつダンサブルなバンドで二極化していた(勿論箱によると思うし、あくまで僕の観測内の話だが)から、ここまでポップなのも珍しかった。UKパンクやニューウェーブやグラムロックがメインの引用先だったStraySheepsですらポップ過ぎると感じたぐらいのライブシーンだった。絶対安全毛布にこの路線でこれほど凄いものを見せつけられたらこちらはまた別の路線で対抗しなければならないと僕は思った。所がまた次はミドルテンポで酩酊感のある粘っこいバックに、自由で奔放な、即興をも思わせるような歌唱、時々シャウトもまじる、が乗っかったサイケデリックかつエモーショナルな楽曲で、彼女の歌の表現力を否応なしに見せつけされ、今までのポップな路線とは違った深淵を覗かせる様な凄みがそこにはあった。演奏が終わると一瞬観客が静まり返ってその後に歓声が起きた。この様な小規模の会場では滅多に見られない反応だ。再びポップな楽曲がはじまり、最後はメソポタミア文明ズの名残を思わせるゴリゴリのファンクナンバーで客の盛り上がりは最高潮に達して終わった。統一感が無いという批判もできたかもしれないが、それは殆ど言い掛かりに近く、思わず誰かに話したくなるかけ値なしで素晴らしいライブといえた。
こんな凄いライブを見せつけられてどうしろと? 彼らがいるなら他のバンドなんて必要ないと思わせるだけのものがそこにはあった。全ての演奏が終わり客電が再びついたあと、僕は友人に「具合が悪い」といって彼の返事も聞かない早さで会場をとび出た。完全に絶対安全毛布だけが目当ての人も少なからずいて、会場からは何人かがぞろぞろと出てきていた。僕と彼らの差は歴然だった。
いつものパターンで、電車に乗って人波に揉まれながら帰るのが嫌になり歩いて帰ることにした。とりあえず北上だ。渋谷から新宿までを目指す。厄介な事に、くるくると動き回る彼女の生き生きとした姿、歌っているときにたまに見せる恍惚とした表情、それは僕にはとても生々しすぎて、あられもない姿を思い起こさせる、は未練がましい気持ちと後悔、二十代前半らしい旺盛な欲望を噴出させ、バンドに対する激しい嫉妬と己の惨めさと相まって、押し合う様にして心の中で禍々しく渦巻き、暴れ回っていた。そんな気持ちも夜の街をがむしゃらに歩き、喧騒や混雑がまばらになり、薄汚れてはいるがそれでも心地は良い都会の夜の春の風に吹きさらされていくうちに、だんだんと浄化されていき、いいライブを見た後のピュアな高揚感が残った。こんな都会のど真ん中でも歩き続けることで不思議と周りに誰もいなくなって本当に一人になれる奇跡的な瞬間がふと訪れる。気づいて立ち止まった僕はぐるりと周りを見渡した。
暗くはない。店と街灯の灯りがある。しかし、そこにはしんとした静けさもあって人の姿や気配はなく、一人だった。いまからでも遅くない。差は歴然だけど、腐らずに続けるべきだと思った。手持ちのカードは悪くない。柳は皆を圧倒する曲をつくり、それを上手く響かせることができるし、南さんも得難いグルーヴをもったドラマーだ。自分の評価は保留しておこう。考えても仕方がない気がする。ただ柳の持ち味が十分に生かされていないのは確かだ。南さんの良さは、十分に出ている。正直彼女のバンドになっている節がある。それはそれでいいが、柳の持ち味は殺されている。我々はもっと遠くに行けるはずだ。絶対安全毛布のように、観客を圧倒するポテンシャルがあるはずだった。少なくとも柳にはそれがある。だから柳と南さんの持ち味を同時に出す必要がある。どうすればよいか。柳は自由奔放、なすがままに活動する事で輝くアーティストだとおもっていた。だが現状を見る限りそれは違う。逆にプロデュース、設計図が必要で、今すぐそれをつくらなくてはならない。
不意に街はまた都会の喧騒を取り戻し、五感に新たな刺激を吹き込んできていた。居ても立ってもいられなくなって、歩くのはもうやめて最寄りの地下鉄に飛び込んですぐに家に帰り、机の上に駅前のスーパーの文具コーナーでつい先ほど買ったまっさらなノートを広げた。その時点では可能性は柳をバンドに誘った時と同じく、無限大だった。ワクワクしていた。だが、想像力が自由で無軌道な飛翔を続けているのを地上からなんとかして捕まえ、鳥かごに入れて、いつでもじっくりと眺められるようにするのは難しく、その鱗片すら紙の上に落とし込むことすら出来ずに机の上のまっさらなノートの前で僕は考え込んでしまった。前に進むのに必要なのは具体性だった。でも何にも出てこない。だが、このまま引き下がることは出来ない。疲れていて寝てしまいたかったが起きて何か糸口を見つけたい。そうしないと一生ずっと後悔する。いまかろうじて指先に残っている確信めいたものの感触は、寝て起きたらきっと消えている。それは、夜、本当に寝る直前で思いついた曲のアイデア、アレンジ、歌詞の断片、イメージ、を紙や録音物として残すことなく睡魔に負けてしまった次の日の朝、それらは確かにあったという微かな記憶だけ(ひどい時はそれすらもなく二、三日後にふっと思い出す、なんの手がかりもなく)を残し、霧散してしまっている、という苦い経験からどうしても避けたかった。とりあえず何を目指したいのか、どうなりたいのかぐらいはっきりさせる必要があった。StraySheepsのコンセプトははっきりしていた。アトラクションズ時代のエルビス・コステロ、初期、中期XTC、blur、攻撃的でいてポップなバンドサウンド、バンド内で複数のシンガーとソングライター。高岸と僕が描いていた絵図。そこにRoxy Musicフリークの石田さんが加わった。彼女はボーカルも作曲も出来た。初期、中期Roxy Musicの音楽性は僕らのコンセプトに合致していた。高岸からしたらもう少しギターに刺激的なサウンドが欲しかったのかもしれない。アベフトシ、ウィルコ・ジョンソン、アンディ・ギルからの影響を隠さない、鋭いカッティングで攻撃的なサウンドをもたらしてくれるギタリスト、花田をバンドに迎え入れた(そして僕が去った)。高岸とは違い、錦に明確なビジョンがあったかというとそうでもない。その時々にできた曲をただ披露していたし、その方向性はバラバラだった。その点は柳にも共通している。それもあって錦をビジョナリーと勘違いし、あの文化祭ライブの後接触してきて、彼女に導いてもらおうとした連中とのバンドはことごとくあのライブの素晴らしさを再現できず、幻を追い求め続け、フラストレーションを抱えたまま空中分解していった。その点、リバーポートソング、あの文化祭だけの錦と柳と僕のバンド、の場合、錦の作った曲をある程度選別し、あの三人のメンバーの構成、そしてそれぞれの特性を活かせるようにアレンジを加え、錦の楽曲を最大限活かせる様に脇を固めたのは柳と僕だった。柳は誰かに楽曲のアレンジや、曲自体の底上げをするアドバイスやアイデアなどにも長けていたが、自身の楽曲に対しては興味の対象がどんどん他に移っていくからか非常に無関心というか、錦の曲に向き合ったような熱心さはなかった。その時はおもいもしなかったが、彼には意外と自分の曲に対する照れがあるのかもしれない。もしかしたら何か方向性のアイデアが有れば柳も自分の曲に対してもっと具体的なアイデアが出てくるのかもしれない。という事でまずは方向性だ。原点に立ち返ると柳を誘ったのは、StraySheepsの時にも高岸と共有していた、作曲や作詞が出来るメンバーが二人以上いて、自分が作った曲は基本自分で歌うというスタイルのバンドが理想像だったからと、錦に感じたように柳の音楽的才能を、彼の作った曲を何とかして世に出したいという思いからだった。現状はどうだろうか。さっき思ったとおり、僕が自分の曲を作ってW3で披露することは殆どなく、ライブは柳の作った曲だけになっていたし、柳の曲を初めて聴いた時の僕の衝撃をそのまま増幅させるようなバンドでもなく、南さんのドラムにあわせたようなシンプルでポップなロックを展開するバンドになっていた。もちろんそれはそれで悪くはないのだが、絶対安全毛布やStraySheepsに対抗するには弱かった(対抗する必要もないのだが)。我々が彼らがライブハウスで皆に与えている衝撃に及ばないのは明らかだった。
僕は広げたノートに以上のことを書き出したが、ノートのマス目がまず邪魔に思えたのと、A4のノートの見開きだけでは、これから書くことがおさまらなさそうだったから、せっかく買ってきたノートだったがもうそれは不要になり(結局は後で日誌として活用することになったが)、大きめのまっさらな紙、画用紙のようなものが必要だったが、当然そんなものは家にはなく、二十四時間やっている駅前のスーパーの二階の日用品コーナーに文具があったのでそこまで行こうかとおもったが、スーパーは四六時中空いているが二階は十時までだったような気がして、ダメ元でいってみることも考えて悩んでいるうちに実家から昨年末に送られてきて、二月のまんまでとまってしまっている壁にかかった大判のカレンダー、ありがたいことにつるつるとした丈夫なものではなく、ボールペンで十分に書き込めるような無印良品っぽさがあるベージュの厚紙仕様、が目についた。早速そのカレンダーを四月現在にアップデートし、ちぎったカレンダーを裏紙とすることで、大きめの紙を二枚作り出すとそのうちの一枚の中心左側に、
・南さんのドラムにあわせたシンプルでポップなロック
・柳がW3でジャムって適当に作った曲が中心
と書きまるで囲むと、右側に、
・柳の「凄さ」を全面に押し出した楽曲
・作曲や作詞が出来るメンバーが二人以上、自分が作った曲は基本自分で歌う
と書いて、またまるで囲んで、左側から右側に矢印を書いた。これで左側が現状で、右側が目指すべき目標になった。左側から右側に移行するためにはどうすればいいのか、それを考えていけばよい。改めて眺めてみると、両方とも付け足す項目がまだまだあって、まるで囲んでしまったことをすぐに後悔した。左側の現状の部分に、「ボーカル、作曲は柳のみ」とか「練習は最近二週間に一度あるかないか」とか「柳も南さんもW3をどうしたいのか不明瞭」とか、色々と不満、不穏に思っていることを書きつけた。右側のなりたいバンド像にも「自分がボーカルをとる曲、自作曲をバンドに持ち込む」や「ライブで必ず自分の曲をやるようにする」とか「二人で歌う曲をつくる」「共作曲を作る」「南さんにも可能なら歌ってもらう」とか色々と書きつけて具体的にしていった。また、右側には自分が最高だと思っているバンドやアーティストを例のノートに書き出してみて、その中から自分がやりたいと思えるようなものはどういうものなのかを改めて要素として抜き出して付け足して行った※①。「柳の『凄さ』を全面に押し出した楽曲」という項目も、「凄さ」がなんなのか具体的にする必要があったから、今まで柳が作って僕に披露してくれた曲を思いつく限り一覧にして例のノートにまとめてみた。柳の作った曲を一覧にしてみてみると、彼の曲も錦同様幅は音楽性は結構幅広いが、得意とするところは割と決まっていて、ボブ・ディランやルー・リード、R.E.M.みたいな、シンプルなコードなんだけど、言葉の響きとメロディのさりげないポップさでぐいぐいと聴かせて、圧倒してしまうような曲だった。それこそジョニー・キャッシュやジェフ・バックリーの様に弾き語りで完結してしまう強度、凄みが、楽曲自体と演者である柳自身にそなわっていたため、アレンジがかえって難しい。弾き語りだけで立ち上がってくる世界が、下手なアレンジで矮小化されてしまう危険性が常にそこにあった。じゃあ、それこそボブ・ディランやルー・リード、R.E.M.を参考にすればよい。ここまでまとめるとカレンダーの裏の「凄み」のところから矢印を引っ張って来て先ほど考察したことを要約して書き足していった。作業しているうちに、夜も明けてきて、そろそろ眠くて限界を感じ、風呂は明日起きた時にして、もう寝てしまおうかとと考えたが、ライブで汗をかいていて気持ちが悪かったので、とりあえずシャワーだけでも浴びることにした。錦のパフォーマンスを見て興奮したのと、渋谷と新宿の間で何やら掲示めいたものを受け取ったせいで見えていなかったが、シャワーを浴びながら理想のバンドのCDを並べたそのラインナップを冷静に思い返してみて気づいたのは、当たり前だがそもそも、いいバンドはメンバー全員がそれぞれ重要だという事だ。偉大なバンドは一人の天才がいればそれでいいわけではない。ビートルズは極端すぎる例だが、例えばドアーズなどジム・モリソンばかりが引き合いに出されるが、他のメンバーも全員素晴らしい。サイケデリックな雰囲気のせいでファーストを聴いただけではよくわからないが、『モリソン・ホテル』などの後期の名盤を聴けばしっかりとしたアレンジもできる有能なバンドであることが分かる。ナンバー・ガール。あのメンバーで誰か一人でも欠けたらそれはナンバー・ガールと言えるのか? クラッシュ。ジョー・ストラマーだけが凄いというわけではない。ミック・ジョーンズのボーカルと彼の曲の方が実は好きだったりするし、ミックとジョーの掛け合いが本当に最高だ。ポール・シムノンのカッコいいベースと佇まい。そしてなんといってもトッパー・ヒードンというすばらしいドラマー。彼がいなかったらクラッシュ全盛期の音楽的広がりもここまでの物では無かったろう。YMO、フリッパーズギター、Queen、メンバー全員が曲を書く、とんでもないバンド達。三人の優れた作曲者がいるラルクもそうだ。ザ・バンド。全員が手練れのミュージシャン。三人それぞれに素晴らしいボーカルを有するバンド。TOTO。選りすぐりのスタジオ・ミュージシャン、作曲者の集まり。はっぴいえんど。その後の邦楽史の在り方を永遠に変えてしまったメンバーが集っていた奇跡的バンド。ポリス、ゆらゆら帝国、ニルヴァーナ、ELP、完璧で歪なトライアングル。きりがない。メンバー全員が重要。それが絶対だ。少なくとも僕の好みは。最初その考えで自分も高岸や柳に並ぼうとしていたのだ。だが、錦や柳という圧倒的な「個」に対峙することですっかりその考えを失っていた。その考えで高岸は僕を切った(何度も言うが辞めたのは僕なので被害妄想なのかもしれないが)し、石田さんや花田などの強力なメンバーを集めていた。絶対安全毛布も錦と藤田さんだけがイニシアチブを握っている様には思えず、個々のメンバーの演奏もそれぞれの楽器のアレンジもしっかりしていた(もちろん誰か一人がアレンジを全部考えた可能性もあるが)。シャワーを浴びてスッキリすると、改めてカレンダー裏の右側に大きく「全員が大事」と書き、その周りに「それぞれの個性がちゃんと、演奏、作曲にあらわれており、それが一つに調和している」と付け加えた。
更に細かい部分を付け足して、一応の形になったころにはもう朝になっていて、ベランダに出て外の空気を吸うと、下の歩道にはもうスーツを身にまとった人がちらほら歩き始めていた。そのうちの一人がおもむろに顔をあげ、目が合った。目が合ったが、ただそれだけだった。部屋に戻って出来た表をみてみる。勿論これは自分の頭の中で勝手に考えたことであって、他のメンバーが同意してくれているわけでもないし、全くこの通り上手くいくとも思ってはいなかった。ただ思う形とは違ってもいまよりも納得できる場所に到達出来る気はした。とにかくこの内容を全部ではないにしてもある程度、共有し同意を得るか、もしくは近いビジョンを持っているか確認する必要はあると思った。となるとやはり柳と南さんが何を思ってW3の活動を続けているのか実はよくわかっていない、というのが一番の問題な気がしてきた。柳はともかく、南さんとは腹を割ってきちんと話をしなければならない。そしてもう一つどうしても足りないのはバンドとしての厚みだった。僕だけでは柳の楽曲に対抗しうる曲を作り続けるのは正直こころもとないのでもう一人、曲が作れて歌えるような人物が欲しいし、音に厚みをつけて、フォーキーな曲で心置きなく柳が伴奏的なギターを弾きながら歌える体制を整えたかった。そしてメンバーの心当たりは一つだけあったからそこで満足して寝た。起きたときには外はまた暗くなっていた。※自分がその当時好きだったこれらのアルバム。勿論素晴らしい作品ばかりだ。しかし今ではこの偏りが気恥ずかしく思える。時は2000年代半ば。すでにラップは90年代中盤の第一次黄金時代を経験していたし、R&BもNJSを経てネオ・ソウルがでてきていた、テクノはエイフェックス・ツインやスクエアプッシャーの登場、ロックやノイズミュージックとの融合、機材の発達、で新しいフェイズに入っていた。そう、90年代に覚醒したのはロックやメタルなどのバンドミュージックだけではなかった。勿論時代を遡ればジャズもレゲエもあった。だが、それらロック以外のジャンルは僕の眼中にはなかった。勿論、それこそ、ロック以外も柳や錦、高良君などの影響で横目で少しは聴いていた。ただそれらの音楽をバンドミュージックと同列に語れるほど、熱中してはいなかった。そうだったらもっと違っていたかもしれない。今でも一人で何かを続けていたかもしれないし、バンドに拘らずにすんだかもしれない。ただ、この時はバンドミュージック、ロックこそ僕の世界の中での中心だった。やりたいことの全てだった。